- 2025.7.22夏大会、なぎなた部愛知県なぎなた選手権大会(7/20)
- 2025.7.22夏大会、柔道部西尾張大会(7/19)
- 2025.7.18よつば小学校の校歌をつくろう(7/18)
- 2025.7.181学期終業式(7/18)
- 2025.7.18セレクトアイス(7/16)
 |
||

学校公開日&修学旅行説明会(5月16日)

学校公開日に多くの保護者の方にお越しいただきました。新しい学年になって二度目です。4月にご覧になった時と比べ、子どもたちの様子はどうだったでしょうか。4月の授業参観は担任を知っていただくという意味もあり、すべてのクラスで担任の授業を見ていただきましたが、今回は普段行われているのと同じように教科担任の授業をご覧いただきました。そういう意味では初めてお子さんが中学にあがった保護者の方は新鮮だったのではないでしょうか。担任以外の先生の名前もご家庭で耳にされることもあると思います。これをきっかけに話に花が咲くことを期待します。
授業だけではなく、教室内外の掲示物もご覧いただけたでしょうか。学級目標やこれから行う行事の資料など、まさに子どもたちの様子が「目に浮かぶ」環境整備が少しずつできあがりつつあります。
そして6時間目には、5月29日(月)から行く3年生の修学旅行の説明会に、こちらも多くの方にご参加いただきました。親子が隣どうしに座り、説明にそってしおりを見ていきます。時折、互いに額を寄せ合って確認し合う様子がとてもほほえましく思えました。きっといい修学旅行になると思います。
地域の一員として(5月14日)
学区の規模が違いますから、会場の雰囲気も違いますが、小さな子からお年寄りまでが同じ場所に集い、繰り広げられる競技に声援を送ったり拍手をしたりと、都市部ではなかなか見られなくなった温かい風景がそこにはありました。そんな中で、係をしている中学生も、よく動いてくれました。徒競走で走ってくる小学生を、
「こっち、こっち」
と誘導する子。器具を出し決められた場所にセットする係。パン食い競争では、小さな子が走ってくると、パンを吊るしてある棒を低くしてあげる優しさも忘れませんでした。
地域あっての弥富中。今日はちょっと恩返しができたでしょうか。そして、子どもたちの成長もご覧いただけたでしょうか。



看護宣誓式(5月13日)

5月12日が「国際看護師の日」ということを知っている人は少なくても、その日がある看護師の誕生日だということを知っている人が少なくても、ナイチンゲールというその看護師の名を知っている人は多くいると思います。
毎年この時期に、看護科(全日制)と衛生看護科(昼間定時制)をもつ愛知黎明高校では病院での臨地実習に出かける前の「看護宣誓式」が行われ、そこに出席しました。
白衣に身を包み、一人一人が一本のろうそくを手にし宣誓する姿は、これから始まる実習の不安を感じさせない凛としたものでした。校長先生や来賓の方の祝辞も、ご自身の“患者”としての経験から、看護技術よりも人として患者さんにどう寄り添うかを説いてみえ、心うたれました。
中学校の3年間を終えると、子どもたちはそれぞれの選んだ道へ進んでいきます。そこで何を学びどう成長していくか、こういう機会を通して見ることができとても大切な時間となりました。
式場まで案内してくれたのは本校の卒業生でした。中学校時代と変わらない笑顔で迎えてくれ、
「友達たくさんできました」
「階段で足をくじいてしまって…」
話し方もまったく変わっていませんでしたが、自分のことや家族のことを話すその様子に成長を感じ、着実に夢に向かって歩んでいると、確信できました。
修学旅行に向けて ~表と裏~(5月12日)
廊下には、各学級で相談し合い決定した見学地の写真が紹介されています。
一方印刷室では、先生たちが生徒に配付するしおりの印刷をしています。来週には、3年生の手元に届けられる予定です。
先生たちも楽しみなのでしょうか、200枚以上を何ページも印刷する作業でも自然と笑顔がこぼれてしまうようです。(遊びにいくのではないのですよ)



せっかくの作品だから(5月12日)
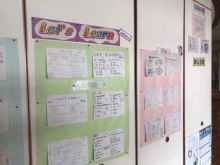
昨年とのことです。生徒会が一年間の総括をした時に、広報委員会から、「Let’s learn があまり読んでもらえなかった」というものがありました。職員でその理由を考えたところ、「掲示してある場所がよくないんじゃないか」という意見が出ました。
そこで、今年はその場所を、子どもたちの下駄箱からすぐのところにしました。これなら、登校してすぐに目にとまり読んでくれるんじゃないかと」。そして、今年の第1号ができ上がったことを契機に場所を変えました。「担任の先生の印象は?」など、おもしろい企画もあります。
子どもたちのその思いを実現してくれる先生方の気持ちがうれしいですね。
不思議???(5月11日)

不思議なことがありました。
1年生の子が体育館と校舎をつなぐ渡り廊下を歩いている時に1羽の鳥を見つけました。ここまでならよくある光景です。しかし、その鳥がいた場所がとても不思議な場所だったのです…。校舎の北側、体育館に面したところにエアコンの室外機を集中的に置いてあるスペースがあり、そこには大型の室外機が10機以上あります。その中のひとつ、しかも室外機のファンに異物が挟まらないように防ぐガードの中にその鳥はいました。ガードはねじでしっかり固定されていて、どこにも穴は開いていません。幸い今の時期はエアコンは使っていませんのでファンは回っていませんから、そのファンの上で羽根をばたつかせていました。
校務主任が脚立にのぼり、自分の背丈よりも高い室外機のカバーを外し、
「ほら、逃げて!」
と手を出しますが、逆にそれにおびえて奥の方へいってしまいます。そんなことを数回やっているうちに、少しの隙間から鳥は出て行きました。
でも、いったいどこから入ったのでしょう…。まさか、卵がうみつけられ、室外機の中でひながかえり大きくなったとか…。いやいや、まさか。ちなみに鳥はセキレイのようでした。
喜んでくれるかな?(5月11日)

朝、登校する子の中に大きなダンボールを抱えてくる子が数人いました。
「それ、おもちゃ作りで使うの?」
「はい!」
毎年、3年生がこの時期の家庭科の授業で幼児のおもちゃ作りを実習します。事前にどういうものを作るかを考え、簡単な設計図のようなものも描き、必要な材料を各自で用意しました。ダンボール、フェルト、ペットボトルなどを切ったり貼ったり、縫ったりと黙々と作業をしていました。作るおもちゃも材料もそれぞれ違いますが、皆、頭の中には、「喜んでくれるかな?」「遊びやすいかな?」「危なくないかな?」と小さな子の笑顔を思い浮かべながら作っているようでした。優しい表情からそれが伝わってきます。
練習法も時代とともに(5月10日)

昭和50年代の部活動の練習といえば「うさぎとび」が定番でした。そして、練習中に水を飲もうものなら、
「こらー!」
と叱られたものでした。私の同級生野球部だった子は、「肩を冷やすから」という理由で体育の水泳の授業はすべて見学でした。
それが当たり前だった時代の人から見ると、今の部活動はどう映っているでしょうか。
陸上部が黄色や紫色の大きなゴムボールに乗って“遊んでいる”ようでした。実際に楽しそうな声も聞こえます。でも、これはちゃんとした練習で体幹を鍛えることをねらいとした「バランスボール」です。スポーツ選手やトレーニングジムなどで多く取り入れられ、その効果も高いことから学校の部活動に取り入れるところも増えてきているようです。
入った!(5月10日)

少しずつ日中の気温が高くなり、教室だけでなく職員室も窓を開けることが多くなりました。
そんな4時間目、なにやらにぎやかな声が聞こえてきます、窓からのぞいてみるとI組・J組の子たちが丸い円盤状のものを投げて、その先にあるかごに入れています。正式な名前は分かりませんが、ディスクゴルフのような遊びです。特別支援学級の子たちにとって、指先や四肢を使うことや集中して物事に取り組むことはとても大切な活動で、こうしたゲームを通してそれを身につけようという活動です。
最初は円盤のようなディスクをうまく投げられなかった子も、手首の使い方などをアドバイスするとみるみるうちに上達し、
「入った!」
他の子や先生たちから拍手やハイタッチ。続けて何枚も入れる子もいました。







