「ようこそ広島へ。カープの優勝のお祝いに来てくださりありがとうございます」
と笑顔で迎えてくださいました。町中にはそんな横断幕もいたるところにありました。
でも、浮かれたやりとりはすぐに終わり、市内を進むにつれ、戦争や原爆に関連する施設や話を聞くにつれ、バス内は自然と静かになりました。そして、原爆ドームの真横にある相生橋の上にバスを停め、そこで昼食です。この研修のお昼は「しげるちゃん弁当」です。これは、8月6日の朝、お弁当を持って出かけた折免滋(おりめんしげる)くんがそのお弁当を口にするとこなく原爆により亡くなったという事実をもとづき再現されたものです。
初めてそれを見た子どもたちからは、
「えぇ、こんだけ?」
「俺、夜、たくさん食べよ!」
という声も出ました。今の子どもたちの正直な声ですね。でも、それすら許されないのが戦争なのです。
子どもたちはこれから平和資料館へ入り、その後、平和公園内を巡ります。







 清掃が終わり、これから5時間目という時間に自転車小屋から声がします。見ると、2年生が次々に帰っていきます。明日からの広島研修に備えての早帰りです。表情を見ると、どの子も笑顔でした。
清掃が終わり、これから5時間目という時間に自転車小屋から声がします。見ると、2年生が次々に帰っていきます。明日からの広島研修に備えての早帰りです。表情を見ると、どの子も笑顔でした。




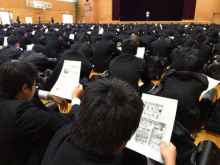 弥富中は他の学校にあるような自転車通学区域がありません。校舎を移転した際に、全校生徒の自転車を収容できるだけの自転車置き場をつくっていただいたおかげで、全員が自転車による通学が可能です。それはとてもありがたいことです。
弥富中は他の学校にあるような自転車通学区域がありません。校舎を移転した際に、全校生徒の自転車を収容できるだけの自転車置き場をつくっていただいたおかげで、全員が自転車による通学が可能です。それはとてもありがたいことです。