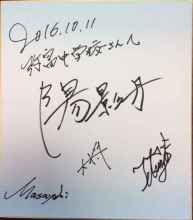子どもたちにとっては今年になって2度目です。1学期の終業式の直前にその音を聞いています。それもあって、子どもたちの避難行動はずばらしいものでした。体育の授業をしていた子は、建物から離れたところにかたまってしゃがみ、移動中の子たちは、持っていた教科書やファイルなどで頭をおおいました。それぞれの教室でも机の下にもぐり、“自分の命は自分で守る”という最初の行動をとることができました。
ほどなくして、職員室から、
「先ほどの緊急地震速報は、関東地方で起きた地震によるもののようです。しかし、今後余震がこちらで起きることも考えられますので、十分に気をつけて行動してください」
と、避難を解除する放送を入れると、安堵の声があちらこちらから聞こえました。
来月2日には、弥富中周辺の、大藤保育園・はばたき幼稚園・大藤小学校の子たちが弥富中に避難し、弥富中の校舎3階に避難するという合同避難訓練を計画しています。いざという時に適切な行動がとれるかは、こうした日常の積み重ねが大切だと痛感しました。