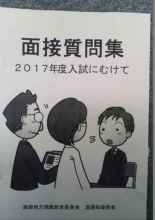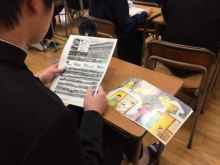「失礼します」
『どうぞ、お入りください』
「お願いします」
『出身校と名前をお願いします』
「弥富中学校から来ました◯◯です。」
『どうぞ、おかけください』
緊張した面持ちで、第1会議室の椅子に座ります。
『本校を受験する志望理由を述べてください』
「はい。僕の将来の夢は・・・・・」
今年度もいよいよ進路に向けての面接練習が、今日から始まりました。
面接官に扮した教師を前に、一生懸命答える姿がとても初々しいです。
事前に『面接質問集』で、志望校の面接内容を事前学習し、答える内容もだいたいは準備はしていますが、実際の場面に近くなると緊張もかなり高くなります。
「怖かった~!」
面接練習を終えて廊下に出た生徒の第一声。
叱られたわけでも怒られたわけでもありませんが、初めての経験で精神的にどっと疲れたのでしょう。正直な心の声です。
こうして進路に向けた新しい経験を積みながら、成長していくのでしょうね。大きくなった背中に、思わず「頑張れ!」と応援の声をかけたくなりました。