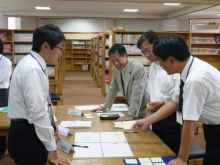朝の低気温が10度を割るようになってきました。これまで開け放っていた教室の扉も、しっかり閉じられるようになってきました。今日はなおさらそんな教室が多くありました。実力テストだったからです。
中間テストや期末テストとは違い、一日に一気に5教科を行います。テスト範囲も「これまで学習したところ全部」とまさに実力が試されるテストです。張りつめた緊張感が漂う一日でした。
 |
||

朝の低気温が10度を割るようになってきました。これまで開け放っていた教室の扉も、しっかり閉じられるようになってきました。今日はなおさらそんな教室が多くありました。実力テストだったからです。
中間テストや期末テストとは違い、一日に一気に5教科を行います。テスト範囲も「これまで学習したところ全部」とまさに実力が試されるテストです。張りつめた緊張感が漂う一日でした。

給食の時間が終わると、いつもはほっとひと息つけるはずの栄養士が、今日はどことなく緊張しています。それもそのはず。5時間目に3年生で「朝食を食べよう」というテーマで授業をするからです。
“食育”という言葉があるように、今、食の重要性が叫ばれています。学校にも、以前は栄養士でしたが、そこに「教える」ことの研修も受けた栄養教諭が配置されるようになりました。弥富中もそのひとつです。その栄養教諭がクラスに出向き、直接、子どもたちに食の大切さ、とりわけ朝食の重要性を伝えました。
84.9%
これは春に行った調査で明らかになった、本校の朝食を食べてくる生徒の割合です。多いと思われるかもしれませんが、育ち盛りの子どもたち。限りなく100%に近づけたいものです。

中間テストが終わってほっとひと息ついた3時間目に、もうひとつの大事なアンケートを行いました。1学期にも行った「Q-Uアンケート」です。
以前にも説明したように、これは集団の中での生活に満足しているか、居心地がよいかなどをはかるものです。弥富中では年に2回実施しています。この時期に行うのは、学校祭でひとつの目標に向かって進んでいた時期が終わり、その間の慌しい日々の中で、学級の中に自分の居場所を見失いかけている子、友人関係の変化で困ったときに相談できる友人が少なくなっている子、次の目標を見出せないでいる子などを、担任が日ごろの観察していることとあわせて、知るためです。また、これをもとに教育相談をします。