
2年生の子どもたちを乗せた新幹線は定刻に広島に着きました。ここ数年で建て替えた広島駅は、
「思っていた広島のイメージと違うでしょ」
と言われるほどきれいな街でした。
そこから平和記念公園へ向かうバスの中で「しげるちゃん弁当」をいただきました。しげるちゃん弁当とは、被災地から見つかった真っ黒に焦げた弁当箱の持ち主、折免滋(おりめん しげる)くん、(当時中学1年生)のお弁当を再現したと言われるものです。食べ盛りの現代の子どもたちには物足りない量、味 ですが、少しでも当時の様子を感じてほしいという思いで、ずっとこの広島研修1日目のお弁当として体験しています。
ですが、少しでも当時の様子を感じてほしいという思いで、ずっとこの広島研修1日目のお弁当として体験しています。
「おいしいじゃん」
という声も聞かれましたが、おそらく、今風に味付けもしてあるからだと思いますが、あっという間に食べてしまう量でした。(子ともたちがお腹を空かせてはいけないという配慮で、おにぎりを1個加えてあります)
そして、子どもたちは1日目の目的地、広島平和記念公園へ向かいました。
広島研修1日目①(11月8日)
あと1日(11月7日)
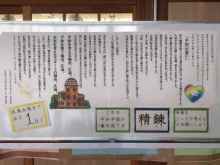
「あと1日」
そんな文字がありました。2年生の広島研修がいよいよ明日に迫ってきました。
MR前にあるホワイトボードに作文が拡大され貼ってありました。それは昨年度の平和祈念式典で読まれた小学生の子の作文でした。題は「平和への誓い」。中ほどにこんな言葉がありました。
平和を考える場所、広島
平和を誓う場所、広島
未来を考えるスタートの場所、広島
とかく私たちは、「広島」というと「原爆が落とされた場所」という過去の事実を結びつけてしまいます。しかし、この小学生が言うように、そうした過去を知り学ぶことで、「これから」を考える場所なんですね。
明日、いよいよその他に足を踏み入れる2年生。そこで何を感じてくれるでしょうか?とても楽しみです。
校内長距離走大会(10月31日)

思っていたほどの青空ではありませんでしたが、予定通り、校内長距離走大会を行うことができました。
この大会のねらいは、「長距離走を通して走る楽しさを味わわせ、完走する喜びを体感させる」です。自分の力に応じた速さでゴールまで走りぬくことを基本とし、その中で走ることが得意な子はどんどん上位をねらい、そうでない子は完走をめざします。運動場を何週も走る練習と違って、学校周辺の道路に出ると、道路の凹凸が足から伝わり、吹く風も場所によってその向きを変えます。男子は6.4km、女子は3.6kmのコースには地域の方々も出てきてくださり、
「がんばれー!」
と声をかけてくださっています。走ることの苦手な子には先生が伴走し一緒に汗を流しました。
 ここ数日に比べると、風もあり少し寒い日となりましたが、子どもたちはそれぞれのペースで最後まで走りぬきました。女子の最後尾を走っていた先生が、
ここ数日に比べると、風もあり少し寒い日となりましたが、子どもたちはそれぞれのペースで最後まで走りぬきました。女子の最後尾を走っていた先生が、
「今年は速くて、ついていくのが大変だった」
と汗をぬぐいながら言っていました。そんな走りをしてくれたことをうれしく思います。
ゴールしてくる子を大きく手を振って迎える見学している子。笑顔で順位カードを渡す係の子。そして、子どもたちのためにジュースとクレープを用意してくださって、ここでも、
「がんばったね」
とねぎらいの言葉をかけてくださったPTA執行委員・正副委員長の方々。そんな人たちに支えられた大会でした。
PTA自転車点検(10月31日)
ご存知のように、弥富中学校は全員が自転車通学をすることが可能です。また、南北に長い校区で自転車は子どもたちの通学にとって大切なものです。しかし、日常の様子を見ていると、キーキーという金属音を鳴らしながら走っている子やタイヤの空気が少ないまま走っている子をよく見かけます。
そんな子どもたちの自転車を一台一台、ペダルを回してチェーン(ベルト)の具合を見たり、ブレーキの効き具合やベルなどを丁寧に点検していただきました。また、空気の少なくなっているタイヤには空気も補充していただきました。修理等が必要な自転車には黄色のカードが付けられましたので、早めの点検や修理をお願いします。


戦争を語り継ぐ(10月23日)

「戦争って怖いもんだよ」
テレビのインタビューに答えるその人は、静かな口調でそう話しました。
今日は2年生の平和学習の一環で、「ピースあいち」から戦争の語り部の方においでいただき、その話をうかがいました。正確には、戦争を体験されたのはその語り部の方ではなく、その方のお父さんでした。太平洋戦争の戦況がいよいよ悪くなり、じわじわと戦争の舞台が本土へと近づいてきた時、沖縄でそれを迎え撃った体験をおもちでした。沖縄戦はとても激しいもので、ガマと呼ばれる洞窟に身を隠すもののそこから生きて出られたのはわずか9人だそうです。その方が、亡くなる直前に、
「戦争が怖いもんだということを、ぜひ伝えてくれ」
と遺言のように娘さんに話したそうで、その娘さんが今日、
「語り部ではなく、語り継ぎ部です」
と、子どもたちに戦争の悲惨さ、怖さを語ってくださいました。
2年生の子たちは、今、来月に行われる広島研修に向けて、事前学習や平和記念公園で捧げる千羽鶴つくり、合唱練習などに取り組んでいます。書物や資料で調べた知識としての戦争と、今日うかがった話とはまるっきり違い、子どもたちは言葉を失っていました。しかし、お父さんが伝えたったことは娘さんから弥富中の2年生に少しだけかもしれませんが確実に受け継がれたように思います。




