「命」をテーマに取り組んできた、今年の道徳の授業。読み物資料だけではなく、直接子どもたちに語りかけてくださる方をお招きし、言葉で、心で、「命」を感じる機会を設けてきました。
1学期=「かけがえのない命」
2学期=「輝く命」
3学期=「つながる命」
1学期に聴いた、中学1年生だった娘さんを交通事故で亡くした佐藤逸代さんの話を聴き、感じたことを綴った作文「命の尊さを考えて」が、警察庁が主催する「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール」で賞をいただきました。その伝達式の様子が今朝の中日新聞に載りました。
同じ話を聴いても、感じ方は人それぞれ。そして、その後の自分の生き方にそれがどう影響するかも人それぞれです。でも、つらい過去を絞り出すように語ってくださった佐藤さんの話がこのような形で子どもたちに届いたことは、その思いが伝わったことの証だと思います。
伝わった「命」(2月20日)
決断!命の一滴(2月19日)
「白血病」
今、この言葉を耳にしない日はありません。水泳の池江選手が、自らその病気にかかっていることを公表してから、連日、テレビや新聞、インターネットでそのことが報じられ、その治療法としての骨髄移植のことも詳しく知るようになりました。
しかし、骨髄移植を希望する人と、それを提供する人をつなぐ「骨髄バンク」が日本に誕生したのは、今からわずか30年前だということを知っている人はいません。
今日は、その骨髄を、家族以外の人に初めて提供した田中重勝さんをお招きしてお話をうかがいました。
1時間目は、その田中さんが主人公として取り上げられている道徳の資料「明日をひらく」(東京書籍)をもとに、それぞれの教室で考えました。まず骨髄移植のおおよそを知ったところで、「骨髄を提供するか、しないか」と問いかけました。子どもたちは迷いました。提供したい、でも怖い、そんな気持ちが心の中で渦巻いていたようです。その後、資料を読み、田中さんの心の変化を考えました。
そして、そこから4時間後。その田中さんが子どもたちの前に立ち、その時の気持ちを語ってくださいました。骨髄バンクから電話がかかってきた時は、登録したことを忘れていたそうです。しかし、その話を二人のお子さんにし、
「お父さんは人の役に立つんだ」
 と言った時のお子さんの顔が忘れられず、日本で初めて、顔も名前も分からない“他人”への提供に踏み切ったそうです。
と言った時のお子さんの顔が忘れられず、日本で初めて、顔も名前も分からない“他人”への提供に踏み切ったそうです。
子どもたちはそんな田中さんの話を真剣なまなざしで聞いていました。田中さんの迷い、田中さんの決断、そして救われた命。
最後に、子どもたちの中から、
「どうして提供しようと思ったのですか」
という質問に、
「同じ命だからです」
と柔和な表情で答えてくださいました。
避難訓練(2月18日)
3時間目の授業を終え、多くの子が4時間目のために移動したり廊下で友だちとおしゃべりをしたりしていた時でした。
「リリリリリリ!」
 という音が校内に鳴り響きました。一瞬、何の音なのか、何が起きたのか分からず、友だちと顔を見合わせる子、きょろきょろする子。でも、ほとんどの子はその異常さに気づき、その場にしゃがみました。表情はとても不安げです。
という音が校内に鳴り響きました。一瞬、何の音なのか、何が起きたのか分からず、友だちと顔を見合わせる子、きょろきょろする子。でも、ほとんどの子はその異常さに気づき、その場にしゃがみました。表情はとても不安げです。
「火災発生状況を確認しています。その場で静かに待機し、次の指示を待ってください」
そこで初めて火災だということを理解しました。しかし、まだ動けません。その発生場所が分からないからです。
「コンピュータ室で火災が発生しました。昇降口は使えません。安全に運動場へ避難してください」
コンピュータ室のすぐ横に昇降口があるので、いつも使っている避難経路が使えません。いつもの感覚で昇降口に来た子がいましたが、
「ここは火元から近いから使えないよ」
と帰しました。子どもたちの近くにいた先生が、中庭や1階の3年生の教室へ誘導し、運動場へ出しました。3階からは1年生が非常階段を使っています。
6分20秒。全員が運動場南側に無事避難しました。
・まず、自分の命を自分で守る
・どこで何が起きたのか、その情報を聞く
・安全な経路で避難する
今年3回目の避難訓練は、そんなとっさの行動がとることができるか、子どもたちはもちろん、教職員にも伝えずに行いました。
教室に戻り、阪神淡路大震災を大阪で経験した教員の体験談を聞き、今日の訓練を振り返りました。
3年間のベストを尽くして(2月14日)

1、2年生は学年末テスト2日目を迎えました。そして、今日はそこに3年生の卒業テストが加わりました。学年末テストは7教科、卒業テストは5教科ですので、このような日程のずれが生まれています。
3年生にとっては、これが最後の定期テスト。約3分の2がこれからまだ公立高校の入試を控えていることもあり、例年、この卒業テストはその公立高校の入試を想定したものにしてあります。まさに、本番さながら、といった状況です。
担任もそれを子どもたちに意識させるために、声をかけています。あるクラスでは、黒板に「最後まで、3年間のペストを尽くす」と書かれていました。そうです。この日まで積み重ねてきたものをこの時間に凝縮させる、まさにそんなふうに臨んでいました。
3時間のテストを終えた子どもたちを優しく迎えたのは給食です。今日は3年生のリクエスト第1位の「あげパン」でした。その名のとおり、運気も上がりますように!
もうひとつの緊張感(2月13日)
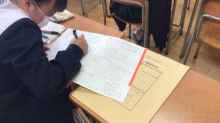
1・2年生が学年末テストに向き合っている頃、1階の3年生の教室では、それと同じような緊張感が漂っていました。
その緊張感の正体は「願書」です。大きなA3版のものに赤いラインが入っているのが特徴的な公立高校の入学願書です。ほぼ同じ記入欄が右と左の並んでいます。Aグループ、Bグループからそれぞれ1校ずつ受検することができます。1校しか受けない子は、右側に大きく斜線が引いてあります。すでに家で下書きを済ませていて、それを担任が一字一字確認をしたものを清書していました。一文字書くごとに、
「ふーっ」
と大きく息を吐き、ペンを持つ手を二度三度振ります。自分の進路を決める大切な書類です。緊張するのも無理はありません。でも、こうしたステップが夢の実現に欠かせないのだと思います。





